2023年M-1グランプリにて、初代王者・中川家以来のトップバッターで優勝という、圧倒的強さを見せつけた超新星・令和ロマン。ボケを担当し、自他ともに認める「お笑いオタク」の髙比良くるまが、その鋭い観察眼と分析力で「漫才」について考え尽くします
【第2回】「様式美と意外性」東西の漫才の違いとは
コレカラをご覧の皆さん。くるまです。
お笑いを考えすぎる当連載も遂に第二回。
前回は季節外れのM-1考察を敢行しまして↓
令和ロマン髙比良くるまの漫才過剰考察|第1回
なんとか誰のお叱りも受けずに生き延びることに成功。
せっかくなので今回分も合わせて史上最薄の書籍を作れたらな、と。
薄すぎてコミケに回されたらな、と。
集まったお客様の蒸気から積乱雲生まれて中からラピュタ出てきたらな、と。
「人間が想像できることは、人間が必ず実現できる」
〜 ジュール・ヴェルヌ 〜
さて、今回も過剰に漫才を考察して行こう、ということですけども。
んー。歯切れが悪いですよね。やっぱりこういう時は、「過剰に考察していかなあかんなあ言うてやってますけど」ですよね。
「いかな」と「あかん」と「言うて」の完璧なフロー。耳心地。
これが関西弁の強い魅力ですよね。
関東漫才師たちはこの魔法とどう戦うか、常々考えさせられているのです。

「天才は裸足なことが多いですからね」と漫画『デスノート』のLを意識
ということで今回は「東西の漫才の違い」について今一度考え直してみようと思います。
主に大阪と東京でどう漫才が違っているのか、客質は如何に異なるのか、などなど。
先人たちによって散々語られている分野だとは思いますが、2023年、東西で割と満遍なく漫才中の私の立場から、新たな答えが飛び出りゃラッキー。
「人間が想像できることは、人間が必ず実現できるんだって」
〜 ジュール・ヴェルヌの友だち 〜
先述の通り、まずシンプルに音が違いますよねえ。
大阪弁という漫才における「標準語」。
当たり前っちゃ当たり前なんですけど本当に重要でして、江戸元禄期に文化と共に花開いたとされる大阪弁はとにかく漫才向きなんです。
商人の街で磨かれ続けたセールストーク用の言葉たちは、お客さんの懐に速く、短く飛び込めるデザインになっています。
目を「メェ」、手を「テェ」のように、母音が伸びることで音を切らずに次の言葉に繋がっています。
それを漫才に落とし込むと、同じ台詞でも音的に短く済むため、間を取ってしゃべることも出来るし、さらに違う台詞を詰め込むこともできる。
アクセントが語尾にあるので、語頭を少し端折っても伝わりやすい。
「なんでだよ」は「なん」にアクセントがあるのでそこと前のボケが被ると分かりづらいですが、「なんでやねん」は「やねん」が大事なのでぶつかっても大丈夫。
だから「っでやねん」くらいしか聞こえなくても平気。ダイアンの津田さんとか常にそう。
まあ洋楽と邦楽の違いみたいなもんですね。同じ意味でも英語の方がギュッと詰まってる。
この質量が大事なんですよね漫才においては。
ただの会話の質量を100とした時に、大阪弁を使うだけで120くらいに膨らむ、そのオーバーした20が観客に「普通の会話ではなく、作品性がある」と思わせる。
極論何もボケなくても、ちょっとすごいことしてる感あるんですよね。
最近で言えば金属バットの友保さんの「しゃーで」とかですかねえ。
標準語を並べても100喋ったら100のまま。
だからって西のスピード感に対抗しようとすると、それはただの「早口」になって、会話に不自然さが生じ、聞き取りづらさや分かりづらさへと繋がるわけです。
反対に標準語の良さはボケが際立つことですね。
間違いのないように設計された敬語ベースの言葉たち、その隙間にポンっとボケが入ると、そのギャップが大きい分、聞き手の予想を鮮やかに裏切ることが出来る。
それゆえ会話としてのスピードは出せなくても、ボケ一発のパワーがある。
特にコントに入る漫才では最大限その力が発揮されます。
コント漫才のボケ役は、その場面にそぐわない事をし続けるわけで、ある意味会話としては成り立っていない状態になってしまっています。
それが対話として完成度の高い関西弁だと悪い意味で違和感が生まれてしまうため、関西では「フリ」が重要視され、その流れに沿った範囲でしかボケづらいのですが、言葉として独立している標準語は次々アナーキーにボケていってもそれが成立しやすい。
東京ダイナマイトさん、トータルテンボスさん、メイプル超合金さんなど、文字に起こして読んでみたらだいぶ支離滅裂な会話だと思うんですが、急に面白いこと言う主役と、それ対して反応する相方、という構図が漫才の一つの型になっています。
ボケそうでボケる大阪弁の様式美に対して、ボケなさそうでボケる標準語の意外性。
スピードの大阪、パワーの東京。うん、なんかそれっぽくなってきました。
「人間が想像できることは、人間が必ず実現できる、でしょ?」
〜 ジュール・ヴェルヌが落ち込んだ時に励ましてくれる女の子 〜
漫才のカタログスペックはこれくらいにしといて、次は観客の方も比較していきましょう。
お客さんのリアクション含めて「お笑い」ですので、こちらも重要な要素です。
大阪の方々はやはり漫才慣れしてますよね。テレビでもよくやっているし、新喜劇や他のバラエティ番組なども芸人さん中心で「漫才的」な会話が浸透している。
大阪でご飯食べてる時、隣の席のカップルの会話とかめっちゃ漫才ですしね。
いやこれ今日日そんなことないとか思われがちなんですがホントにそうですよ。
みんなクオリティに差はあれど漫才の「型」を感じます。
物心つく前から空手教えられてるから、普通に喧嘩してもちょっと型出ちゃってるみたいな。
なので逆に「漫才じゃない時間」に厳しい。
東京で活動してた私が関西の劇場に出るようになって最初に感じた違和感は、「ツカミ」がウケないなぁ、という部分でした。特に、ネタに関係のない自己紹介的ツカミ。
それまで関東では、自分たちのことを知らないお客さんが多い時は必ず、コンビ名と個人名を言うだけでなくて、学歴や運動歴などを絡めたボケを入れてから本ネタに入るようにしていました。
そこを疎かにするとお客さんの集中力が低く、ウケにくい傾向にあったからです。5分出番があったら1分はそこに時間を割いていました。
しかし関西ではそこがウケず、まずいと思って更にツカミを追加するもウケず、本ネタが2分ほどしかできずウケず終わる、という地獄を経験しました。
簡単に言うと「そんなんええから早よ漫才見せてや」って思わせてしまってたんでしょうね。
漫才の見方は分かってるからこそ、「ツカミ」が蛇足になってしまってる。
甲子園での試合前に、野球ファン向けにわざわざ野球のルールを説明しているようなものです。

中高時代はラグビー部に所属していたくるま
関西で大事なのは「何をやっているか」。
関東で大事なのは「誰がやっているか」。
ざっくりまとめるとこんな感じでしょうか。
これは関東の人が内容を気にしてない、という訳ではなく、まず漫才に慣れるために人間を認識する必要がある、ということです。
漫才は「会話」という日常を作品化している かなり繊細な芸術であり、これにプロ性を感じて楽しむことは、コントや映像ネタを見るより少し難しい作業。
お笑いファンになって漫才を見る回数を重ねていくと大阪人のように、「今からどっちかがボケてどっちかがツッコむのだろう」という筋が見えてくると思いますが、関東では普段の会話をそこまで構造的に捉えてない人たちが多い訳で、まずはその人間性で笑うことが精一杯なのかと思います。
「人間が実現することは、人間が想像していたことである。」
〜 ジュール・ヴェルヌのパクツイ 〜
発せされる音、そして聴かされる耳。
この組み合わせが更にどう漫才を変容させているのでしょう。
大阪ではスピード言葉を玄人が審査していき、
東京ではパワー言葉を素人に啓蒙していっているような気がします。
お客さんの理解が深い大阪では、漫才を深い地点からスタートできるので、フィクションのラインを高く設定できます。
例えば「刑事と犯人」の漫才コントをする時に、「刑事って憧れますよねえ」という台詞のみでスッとコントに入っても受け入れてくれる。
東京だと「僕が刑事をやるので、犯人をやってほしい」などと理由を明示することで、一応本当のこととして役を演じます。
東京人の私は大阪の先輩方の漫才を初めて見た時、正直「う、ウソつけ〜!」って感じでした。「そんなスピードでツッコめるか〜!」
この時点で漫才ネイティブ達に着いていけてないワケですね。
どんどんラインが上がっていた先に、様々な傑作が生まれていきました。
ブラックマヨネーズさんの「喧嘩」も、格闘技の提案に対しての吉田さんがボケるのは当然として、さらに小杉さんもボケた提案で返し、それに突っ込まずにボケ返す吉田さん、というスーパーフィクション会話を面白く受け入れるという境地まで、漫才と観客が成長を遂げていったのです。
その進歩は受け継がれ、昨年のM-1でのさや香さんのように、引き上げられた漫才偏差値の上で輝く漫才が次々生まれています。
一方で東京漫才は、レベル上げがしづらい環境でそれでも鍛錬を積もうとした結果、よりクローズドな漫才が進化していきます。
初期M-1で言えばおぎやはぎさん然り、POISON GIRL BANDさん然り、観客を迎えにくのではなく、二人で作り上げた異世界へ誘い込むスタイルが心を掴む。
台本はフィクションでも、それを演じる人間はノンフィクションであると思わせ、「本当に変な人たち」がやっていることに価値が付いてくるようになっていく。
そしてそれが近年のM-1チャンピオンの誕生に繋がっていきます。
マヂカルラブリーさん、錦鯉さん、ウエストランドさん、皆その条件を満たしています。
キャラクターが付きやすいことがまた「テレビ的」な強さもあり、漫才の外に出てもそのイメージで活躍しやすいんだと思います。
これほど違う特徴のある二つの漫才、二つのお笑いですが、書いてくうちにその両方を兼ね備えている存在に気が付きました。
ダウンタウンさんです。
大阪的なスピードで加速して、東京的なパワーで世界観を作り込むコントもできる。
そりゃ天下取れるわ。みんなの心に刺さるんだもの。
うわー、千鳥さんもそうだ。
言葉は岡山で、初期M-1で見るネタはどれも尖ったクローズドなネタ。
そこにロケで磨かれた人柄のオープンさが加わってきた。
加わる順番は逆なんですけど、これTHE MANZAI以降になってくると、「あ、この二人が本当に好きなことしてるんだなー」と誰もがその世界を覗くようになって、それがドリーム東西ネタ合戦でのアドリブ祭りで爆ハネした。「蟹宮」と「も宮」のとことか。赤すぎて白、のとことか。
そっからだと思ってるんですよこの千鳥さんの快進撃って。
大阪の技術と東京の…なんというか、愛嬌、見やすさ。
その二つが混ざって乳化してるのが最強ですわ。
マンテカトゥーラですわ。
「人想人必実」
〜 ジュール・ヴェルヌ立高校の校訓 〜
と、まあ、様々な角度から東西の違いを過剰考察させていただきました。
伝統の継承と革新は、案外別の空間で同時並行に行われ、その二つは今、一つに完成しようとしているのかもしれません。
この前の27時間テレビにもそのようなエネルギーを感じました。
私も早く美味しいパスタが作りたくなりましたね。
皆様がご観劇の際は、くれぐれもこんなこと考えないように見ていただければ幸いです。
髙比良くるま
写真・北原千恵美

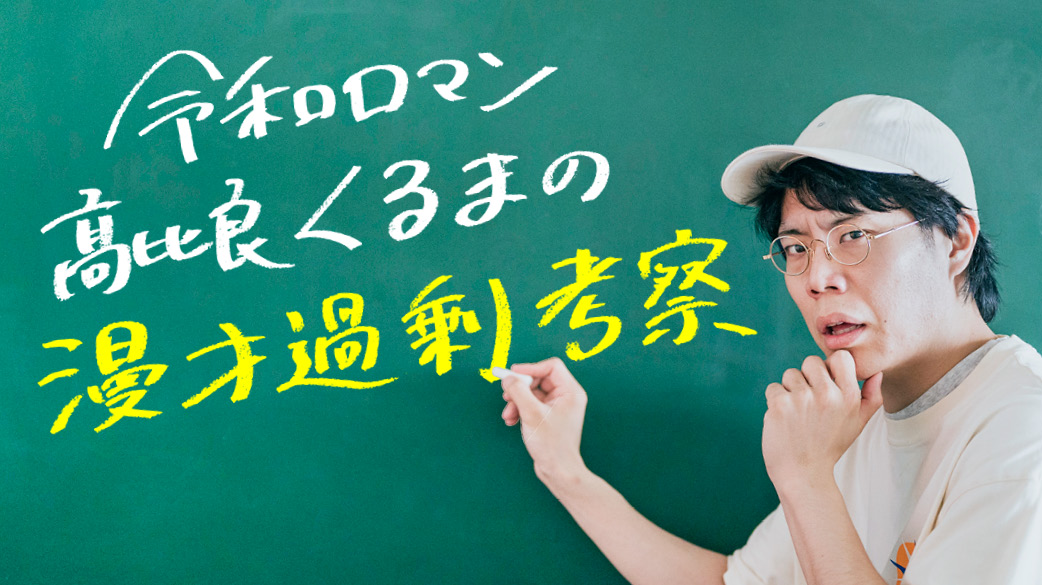
 1994年09月03日生まれ。東京都練馬区出身。芸人。吉本興業所属コンビ・令和ロマンとして活動。東京NSC23期首席。M-1グランプリ2023王者。
1994年09月03日生まれ。東京都練馬区出身。芸人。吉本興業所属コンビ・令和ロマンとして活動。東京NSC23期首席。M-1グランプリ2023王者。