血統書がなくても、ブランド犬種ではなくても、こんなにも魅力的で、愛あふれる犬たちがいます。
み~んな、花まる。佐竹茉莉子さんが出会った、犬と人の物語。
保護犬たちの物語【第8話】ふく
3.11「東日本大震災」後の福島第一原発事故から13年が巡ろうとしていた今年2月23日。埼玉県内の住宅で、1匹の犬がひっそりと息を引き取った。
名前は「ふく」。もしかしたら秋田犬の血が入っていたかもしれない、凛々しいオスの柴犬だった。

キャラメル色の凛々しいふく(またたび家提供)
彼は、18歳を過ぎた1年半前から歩くことが困難となり、家の中で寝たきりだったが、毎夕お父さんとお母さんにぬるま湯で体を洗ってもらうのが日課だった。その日も、お風呂場でいつものようにウトウトしていると思ったら、首がカクンと落ちた。そして、そのまま旅立っていった。死因は「老衰」である。7歳過ぎでこの家にやってきて、呆けもせず12年半をかくしゃくと生きた。
山田政光・貴美子さん夫妻がふくを迎えたのは、2011年4月23日のこと。その前夜10時頃、福島第一原発3キロ圏内の大熊町から、せっぱつまった声の電話を受けたことがきっかけだった。
「犬を飼っていただけないでしょうか。どこもいっぱいいっぱいで連れて帰っても受け入れ先がもうありません。明日から立ち入り禁止となる町です。置いていったら、死ぬ子です」
つてを頼って電話をかけてきた声の主は、当時大熊町に残された犬猫レスキューのため、個人で通っていた塩沢美幸さんである。

大熊町の津波被災地(またたび家提供)
塩沢さんは19日に何度目かの現地入りをして、20日深夜に埼玉に戻ってきていた。だが、大熊町が22日0時から立ち入り禁止に指定となることをニュースで知り、居ても立ってもいられない思いで21日未明に再び大熊町へ。21日はぎりぎりまで現地を回った。
車はすでに、飼い主から委託されて保護した犬猫たちを入れたケージでいっぱいとなっている。保護できなかった犬猫たちには、心の中で慟哭しながら、雨に濡れない場所に大量の餌を置いていくことが、できることのすべてだった。

家の前にいた痩せこけたふく(またたび家提供)
瘦せこけたこの犬は、無人の家の前にいつもいた。その日も、車を見るや一目散に駆け寄る。与える餌をガツガツと食べた。
もう行かなければ。心を鬼にして現地を後にした塩沢さんの車を、茶色の犬は、その日、いつまでも追いかけてきた。
窓を開けると、「どうか連れて行ってください」と懇願するように、車窓に手をかけ、すがった。
だが、塩沢さんの家も預かりボラの家も、どこも満杯でまったく余裕がない。受け入れ先がなくては連れ帰れない。塩沢さんは電話をかけ続けた。貴美子さんにつながったのは、もう夜の10時で、119件目だった。

「連れてって」と車にすがってきたふく(またたび家提供)
貴美子さんは、小さなころからずっと犬を飼ってきて、「チョコ」という愛犬を1月に亡くしたばかりだった。その悲しみの中にあって、今は新しい犬など迎える気はなかったのだが、事情を聞いて、思わず答えていた。
「いいですよ、連れてきてください」
3日間ほとんど寝ていなかった塩沢さんは、パーキングエリアで仮眠をとり、22日朝、山田さん宅に向かった。

大熊町を後にした朝、車窓から外を見るふく(またたび家提供)
受け入れ先を命ぎりぎりで手に入れた犬は助手席におとなしく座り、牛たちがうろつき、亡骸も点在する景色をじっと見つめながら、大熊町を後にした。
政光さんと貴美子さんのもとに、朝やってきた犬は、薄汚れて黒ずんでいた。洗った後は、あばら骨が浮き出ているのが目立った。
福島からやってきたのと、幸福になってほしいとの願いを込めて、名は「ふく」とした。
やってきて3日ほどは、塩沢さんの言った通りおとなしかったが、4~5日たつとよく吠えるようになった。吠えるだけでなく、来客に噛みつく。かなりの本気噛みで、青あざが残るほどだ。皿からこぼれた餌を入れてやろうとした政光さんの手にも噛みつく始末だ。
「番犬として飼われていて、今度はこの家を守ろうとしているのかしら」とも貴美子さんは思ったが、「被災地に残されて、餌も水もなく、外敵から必死で身を守った40日が想像を絶するほど過酷で恐ろしかったせいでは」と思うと、いじらしくてならなかった。

お父さんと朝の散歩(またたび家提供)
「噛み癖はあるし、しっぽも振らないし、おなかも見せないし、甘えない。いわゆる可愛いペットではなかった。でもね、可愛いところもあったの。私に叱られると、目が点になったりして(笑)。私には、一度も噛みつかなかったわね」と、貴美子さんは笑う。
やがて、元の飼い主が判明した。やはり番犬として飼われていたようで、避難先にいる元飼い主に代わり、親族の女性が探し出してくれたのだ。元飼い主との再会をふくは喜んだものの、別れるときに後を追うようなそぶりは見せなかった。事情を悟って「僕はもうここの家の子だ」と察したようだった。「よろしくお願いします」と言って、元飼い主はふくを政光さんたちに託した。

もう家族の一員(山田さん提供)
かかりつけの獣医さんに言われた「叱らずに、とにかく可愛がってやってください」を、夫妻は守った。朝の散歩は政光さんと、夕方の散歩は貴美子さんと。休日は3人で散歩した。先代のチョコは遠くへのお出かけが大好きだったが、ふくは家から離れると、Uターンしたがった。ねぐらを無くす不安がトラウマとして残っていたのかもしれない。
「ごはんを食べるときが一番うれしそうだったかな。魚市場でシャケを買ってきて、焼いてほぐしてごはんと混ぜてやるのが、とりわけお気に入りでした」

18歳のころ。家の中に大きな犬ベッドを置いてもらう(山田さん提供)
そんなふくも、老いていき、18歳を過ぎると、脚が不自由になってきた。亡くなる前の1年ほどは完全室内暮らし。政光さんが抱っこして庭に連れ出し、日向ぼっこをさせていた。
寝たきりになると、鳴き方に少し甘えが混じってきた。抱くことも撫でることもさせるようになる。目に白内障が少し入っただけで、耳も歯も大丈夫だった。
「最後まで、外に人の気配がするとよく吠えて、立派な番犬をしてくれました。寝たきりでもいいから、もうちょっと生きてほしかった。いなくなると、ほんとにさびしいわねえ」と貴美子さんはしみじみと言う。
「いずれ別れの日がやってくるのがずっと嫌だったけれど、とうとう来てしまいました。でも、つらい思いをした後にここにきて幸せだと思ってくれたかな」と、政光さん。
先日、ご近所さんや犬飼い仲間たちと、蕎麦店で「ふくちゃんを偲ぶ会」が開かれた。
「私も噛まれた」「私も!」で盛り上がったそうだ。
塩沢さんは現地でふくと出会ったとき、「生きていてくれてありがとう」と思ったが、19歳7ヶ月まで生きたことも「よくぞ」とほめたたえてやりたい。山田さん夫妻には感謝でいっぱいだ。

保護前、置き餌をむさぼるふく(またたび家提供)
月日の経過とともに被災地に通うボランティアが減っていく中で、塩沢さんは現地に8年間通い続け、犬猫たちのいのちを譲渡先につなげた。現在は、「またたび家」代表として、飼い主のいない猫やセンター収容猫たちの保護譲渡のために活動を続けている。またたび家にいる被災地からの猫は3匹だけとなったが、大熊町での悲惨な光景は今も脳裏からけっして離れることはなく、「人知れず死んでいく子がないように」の思いを強くする。
佐竹茉莉子
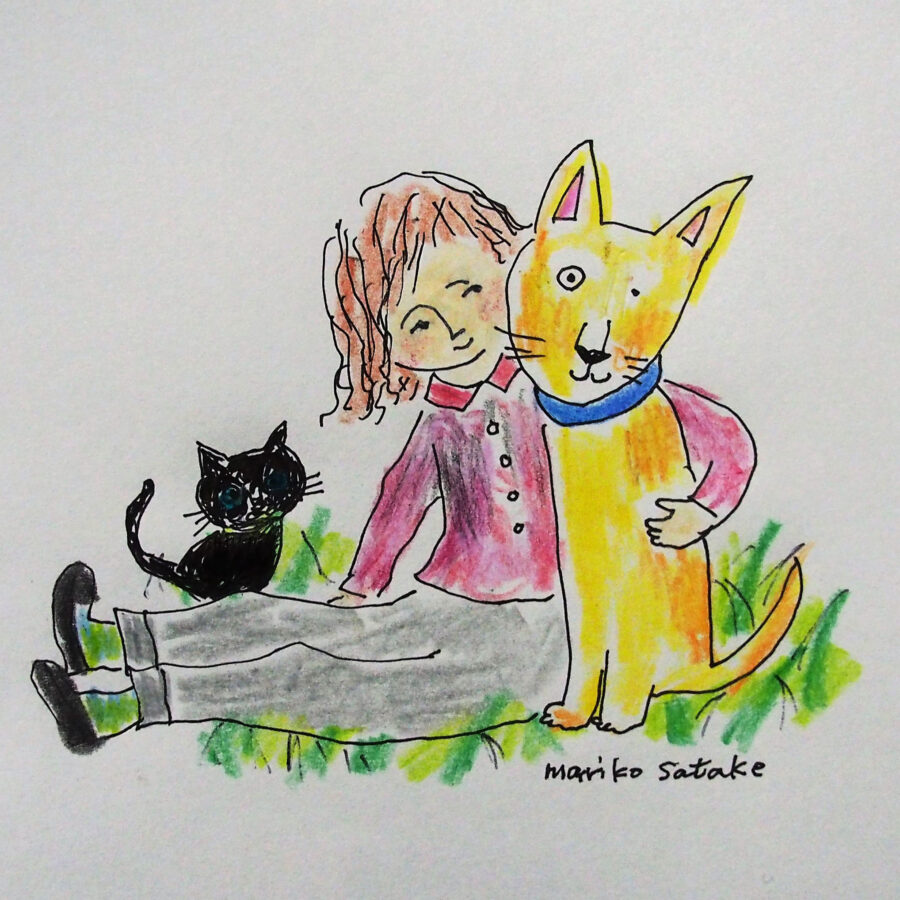
フリーランスのライター。路地や漁村歩きが好き。おもに町々で出会った猫たちと寄り添う人たちとの物語を文と写真で発信している。写真は自己流。保護猫の取材を通して出会った保護犬たちも多い。著書に『猫は奇跡』『猫との約束』『寄りそう猫』『里山の子、さっちゃん』(すべて辰巳出版)など。朝日新聞WEBサイトsippo「猫のいる風景」、フェリシモ猫部「道ばた猫日記」の連載のほか、猫専門誌『猫びより』(辰巳出版)などで執筆多数。
Instagram連載一覧
- 第1話 殺処分寸前で救い出された生後3ヶ月の子犬…今はまるで「大きな猫」|ハチ(9歳)
- 第2話 トイレはすぐに覚えて無駄吠えや争いもなし。「野犬の子たち」が愛情を注がれて巣立っていくまで|野犬5きょうだい
- 第3話 トラばさみの罠にかかって前脚先を切断 今は飼い主さんの愛に満たされ義足で大地を駆ける!|富士子
- 第4話 子犬や子猫たちに愛情をふり注ぎ、いつもうれしそうに笑っていた犬の穏やかな老境|ハッピー(19歳)
- 第5話 野犬の巣穴から保護されるも脳障がいで歩行困難 でもいつでも両脇にパパとママの笑顔があるから、しあわせいっぱい!|みるちゃん(今日で1歳)
- 第6話 自宅全焼でヤケド後も外にぽつんと繋がれっぱなしだった犬 新しい家族と出会い笑顔でお散歩の日々|くま(8歳)
- 第7話 飼い主を亡くし保健所で2年を過ごしたホワイトシェパード 殺処分寸前に引き出され自由な山奥暮らし|才蔵(8歳)
- 第8話 「置いていったら、死ぬ子です」福島第一原発警戒区域でボランティアの車に必死ですがった犬|ふく(19歳7ヶ月で大往生)
- 第9話 「歯茎とペロ」の応酬で烈しくじゃれ合う元野犬の寺犬たちが「仏性」を開くまで|こてつとなむ
- 第10話 生後間もなく段ボール箱で道の駅に捨てられていた兄弟 仲良く年をとってカフェの「箱入り息子」として愛される日々|まる・ひろ(13歳)
- 第11話 人間が怖くてたまらない「噛み犬」だったセンター収容の野犬の子 譲渡先で猫にも大歓迎され一歩一歩「怖いこと」を克服 |小春(8か月)
- 第12話 愛犬を亡くして息子たちは部屋にこもった 家の中を再び明るくしてくれたのは、前の犬と誕生日が同じ全盲の子|ゆめ(もうすぐ2歳)
- 第13話 「怖くてたまらなかったけど、人間ってやさしいのかな」 山中で保護された野犬の子、会社看板犬として楽しく修業中|ゆめ(3歳)
- 第14話 戸外に繋がれたまま放棄された老ピットブル 面倒を見続けた近所の母娘のもとに引き取られ、「可愛い」「大好き」の言葉を浴びて甘える日々|ラッキー(推定14歳)
- 第15話 土手の捨て犬は自分で幸せのシッポをつかんだ「散歩とお母さんの笑顔とおやつ」…これさえあればボクはご機嫌|龍(ロン・12歳)
- 第16話 動物愛護センターから引き出され、早朝のラジオ体操でみんなを癒やす地域のアイドルに|カンナ(10歳)
- 第17話「もう山に返したい」とまで飼い主を悩ませたやらかし放題の犬 弟もできて家族の笑顔の真ん中に|ジャック(3歳)
- 第18話 飼い主は戻ってこなかった…湖岸に遺棄され「拾得物」扱いになった犬が笑顔を取り戻すまで|福(推定2歳)
- 第19話 飼い主を亡くした認知症の犬が里山暮らしの犬猫たちの仲間入り「いっしょにゆっくり歳をとろうね」|あい(推定16歳)

